レガシー半導体は「過去」のものではない!
今、「レガシー半導体」と呼ばれる成熟ノードが注目を集めている。この成熟ノードはもともと市場で重要な役割を果たしていた言わば「過去」のものだ。しかし、現状は依然として重要な役割を果たしているのだ。
事実、28nm 以上のノードを持つレガシー半導体の市場規模は 2022 年時点で約738 億ドル(出典: IC Insights)に達し、2027 年には1000 億ドルを超えると予測されている。では、なぜ今なおレガシー半導体が求められるのか?本記事では、その市場規模、ビジネス戦略、今後の展望について深り下げてみる。
レガシー半導体が生き残っている理由
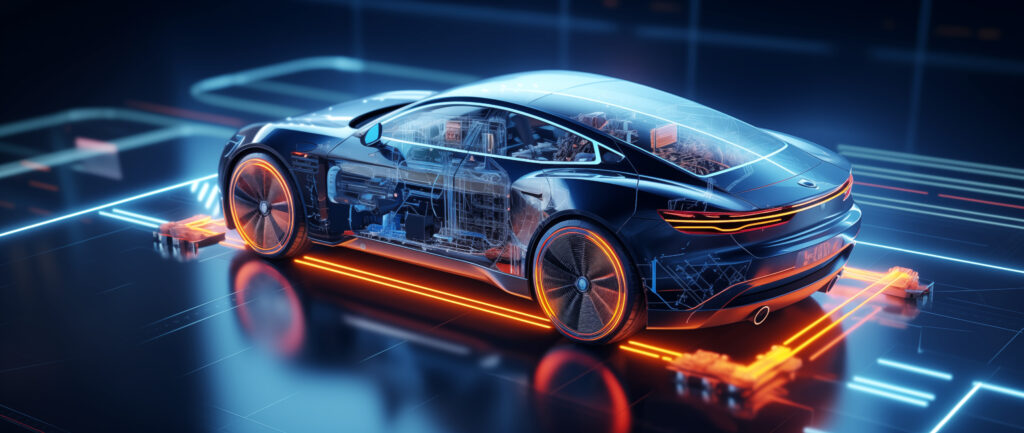
1. 幅広い用途と継続する需要
レガシー半導体は、家電、自動車、産業機器、医療機器など幅広い用途で利用されている。特に以下の分野では、成熟ノードの半導体が不可欠である。
- EV(電気自動車) ADAS(先進運転支援システム)
- 産業用 IoT(IIoT)
- スマートシティ関連機器
例えば、車載 MCU の約 70%は 28nm 以上のノードで製造されており、今後もこの傾向は続くと考えられている(出典: Yole Développement)。
2.製造能力限界と供給不足に対する投資増加

2020 年以降の半導体不足を受け、最先端ノードだけでなく、レガシー半導体の供給不足も深刻化した。特に、日本のユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMC)、米GlobalFoundries(グローバルファウンドリーズ)、Tower Semiconductor(タワーセミコンダクター) などのファウンドリーはフル稼働状態が続いており、台湾の台湾積体電路製造股份有限公司(TSMC) も成熟ノードの生産能力を拡大している。
このため、特に中国は投資が活発になっている。
しかし、レガシーノード向けの新規設備投資は限定的であり、供給不足が長期化するリスクも指摘されている。
3.米中対立の影響と国内生産の強化
米中対立の影響で半導体の供給網が分断されつつある中、各国政府は国内生産の強化に乗り出している。以下にその例を示す。
- 米国の CHIPS Act(出典: 米国商務省)
- 日本の TSMC 熊本工場支援(出典: 経済産業省)
- 欧州の EU Chips Act(出典: 欧州委員会)
特に日本では、ソニー、ルネサス、キオクシアなどがレガシー半導体を軸とした戦略を進めており、2024 年以降も国内生産の強化が期待されている。
レガシー半導体にもある未来

レガシー半導体は、とかく最先端技術の陰に隠れがちだが、多くの産業の根幹を支えているのも事実。今後の市場の鍵となる用途を以下に示す。
- 新たなアプリケーション(EV、スマートシティ、IIoT)への適用
- 地政学リスクを背景とした国内生産の拡大
- エネルギー効率や耐久性を重視したレガシーノードの最適化
最先端半導体が AI や HPC 向けに進化する中、レガシー半導体も求められる用途に適応しながら進化していくと思われる。
このようにレガシー半導体は死なない。それどころか未来さえある。この市場の動向を見極めることが、日本の半導体業界に携わる者にとって大切となるだろう。