2025年秋、中国は「米系AIチップ依存の縮小」を一段と明確化した。2025年7月31日のサイバー空間管理当局(CAC)によるNVIDIA召喚を起点に、9月には大手プラットフォーマーへの購買中止ガイダンスが報じられ、10月には通関監視の強化観測が相次いだ。
現場では、国産CPU/GPUの採用拡大や、規制準拠の下位仕様(ダウングレード)SKU(在庫管理単位)の再評価が並行し、調達・在庫・運用の「設計変更」が進む。
本稿は、①通関監視と調達行動、②下位仕様SKUの再評価、③国産クラウド/国産アクセラレータの受け皿、の三軸で中国の対米半導体戦略(NVIDIA離れ)の現状を時系列に沿って考察する。
2025年7–10月:監視の「強化」へ

まず、ここ直近の中国の動きをまとめる。
• 7月31日:CACがNVIDIAを召喚し、H20に関するセキュリティ懸念を確認との報道あり。この出来事は、以後の監視強化に向けた制度的前段と受け止められた。
• 9月中旬:当局がByteDanceやAlibabaなどにNVIDIA製AIチップの購入停止や既存発注の見直しを促したと報じられ、購買ガイダンス(ソフト)が市場に共有された。ワークステーション向けの中国専用SKU(例:RTX Pro 6000D)と、データセンター向け(H20等)の用途差は明確化が必要、という指摘も広がる。
• 10月上旬:主要港での半導体通関検査の強化が相次いで報じられ、AIアクセラレータ、ネットワークカード、HBM、パッケージ基板等の関連カテゴリーを含む書類精査・現物確認の厳格化が注目を集めた。
実務面では、(a)通関前滞留の増加による計画バッファ前提化、(b)混載の再設計(GPU・NIC・HBM・筐体等の申告分離)、(c)保守スパーの積み増しが広がったとの見方が強い。9月の“ソフト”と10月の“ハード”が両輪となり、下位SKUであっても審査フリーパスではないという前提が共有された。
“下位仕様(規制準拠)”SKUの再評価
2025年に入り、輸出規制枠内で帯域・メモリ・パッケージ仕様を抑えた派生品が相次いで取り沙汰された。HBM非採用(GDDR)や先端パッケージ(例:CoWoS)非前提の設計による価格・入手性の改善が期待された一方で、
• 8月:当局がH20の政府・重要インフラ用途での使用抑制を示したと報じられ、
• 9–10月:購買中止ガイダンスと通関監視強化の観測が重なり、
「規制準拠=採用OK」という単純な等式は成立しにくい、との現場認識が強まった。結果として、調達部門は①代替ベンダの複線化、②品目分割と申告区分の厳密化、③保守スパーの計画的積み増しへ舵を切る。重要なのは、「買える」ことと「使える」ことは別という割り切りだ。
評価軸を入手性>通関容易性>実効性能の順に置き、RFP段階でSLA(応答時間/スループット)、電力(kW/ラック)、ラック密度の「要件適合判定」を前提条件化。適合しない案件は初期で適用除外にするガバナンスが不可欠である。
2025年Q1–9月:内需の受け皿——国産クラウド×国産アクセラレータ

需要の底堅さが続いている。2025年Q1の中国クラウド市場支出は前年比プラス成長と報じられ、生成AIの学習・推論需要が伸長した。Alibaba、Baiduは自社開発チップの学習適用を広げ、China Unicomは、国産AIチップ構成のデータセンターを前面に押し出した。
報道ベースでは、約3,579 PFLOPSで稼働し、将来2万PFLOPS規模への拡張構想も示唆され、計画規模と運用意思の強さが注目を集める。
運用のカギは3点に整理できる。
①ソフトウェア・スタック:CUDA互換・移植、CANN等の成熟度を高め、運用コスト(マイグレーション工数)を抑制。
②モデル最適化:注意のおろそかさ、長文脈最適化、精度–計算量トレードオフの調整で、下位仕様構成でもSLA(サービス品質保証)を満たす設計へ。
③電力・ラック密度:PUE(電力使用効率)改善だけでなく電力契約・受電容量を含む施設設計を実現する。
この結果、「国産クラウドでまず推論・一部学習」→「学習も段階移行」というロードマップ指向が広がり、既存NVIDIA資産の延命・再配置との併存が見え始めた。
2025年9月:NVIDIA依存の“残影”——需要は減少するが、なくならない
9月上旬の報道は、当局の圧力があってもNVIDIA需要は根強いことを示した。CUDAエコシステムを前提とする先端学習ワークロードの完全置換には時間がかかるためだ。一方で、Alibaba/Baiduの自社チップ活用は着実に進み、「依存度は下がるがゼロにはならない」という均衡が見えてきた。
顧客側の基本戦略は、①短期:既存NVIDIA資産の延命・再配置、②中期:国産アクセラレータの併用比率拡大、③長期:モデル/ツールチェーンの国産適合という三段構えである。論点は輸入可否から、通関・適合・監査まで含めたTCOへと移っている。
“NVIDIA資産の活用”と“国産化の進行”の併存が当面の基本形
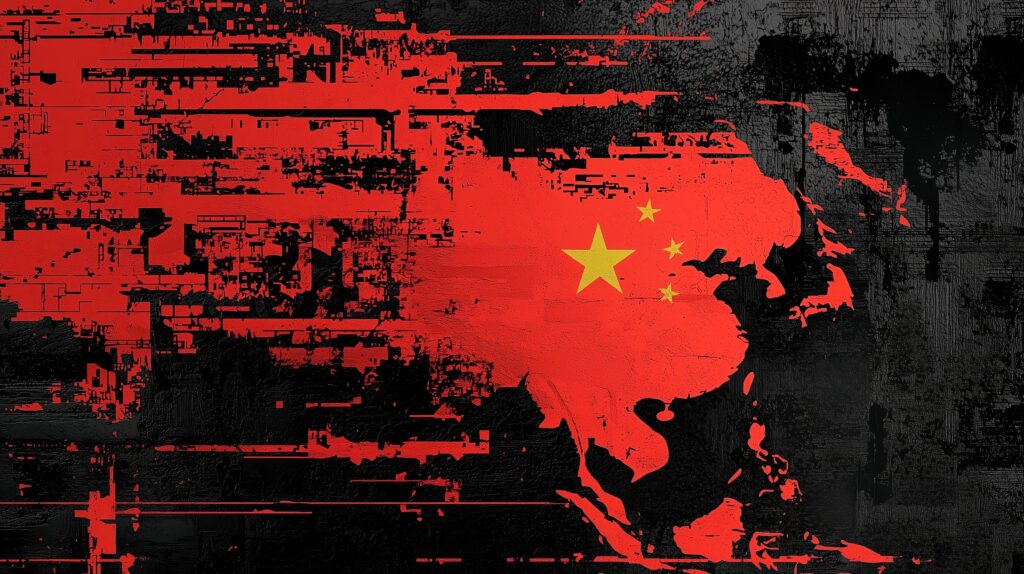
このような2025年7–10月の一連の動きは、ガイドラインから執行へという移行点として受け止められた。下位仕様SKUという“余地”は、審査・運用摩擦で徐々に埋められていく見方が強まる。他方、国産クラウド×国産アクセラレータは「まず推論、つぎに学習」の器として現実味を帯び、“NVIDIA資産の活用”と“国産化の進行”の併存が当面の基本形となる。
三層ポートフォリオ(実務指針)
• 短期:再配置・保守スパー確保、通関前バッファを前提化
• 中期:国産/下位SKU/国際品の複線化と申告区分の厳密化
• 長期:ツールチェーン国産適合、電力・監査前提のTCO最適化(PUE・受電・ラック密度まで一体設計)
勝敗は絶対性能だけでなく、通関・適合・監査を織り込んだ運用設計と在庫設計の巧みさの差で決まる。依存の再配分を前提に、ビジネス摩擦をコストではなく競争優位に変える設計が問われているのだ。
*この記事は以下のサイトを参考に執筆しました。
参考リンク
- China tells tech firms to stop buying Nvidia’s AI chips, FT reports(Reuters, 2025年9月17日)
- Chinese firms still want Nvidia chips despite government pressure not to buy(Reuters, 2025年9月4日)
- 中国、エヌビディアH20製品使用控えるよう要求(Bloomberg日本語版, 2025年8月12日)
- Mainland China’s cloud infrastructure market growth accelerated in Q1 2025(Omdia, 2025年7月10日)
- Alibaba, Baidu begin using own chips to train AI models(Reuters, 2025年9月11日)
- China spotlights major data centre project using domestic chips(Reuters, 2025年9月17日)
- Nvidia to launch cheaper Blackwell AI chip for China after US export curbs(Reuters, 2025年5月24日)
- China’s cyberspace regulator summons Nvidia over H20 chip security risks(Reuters, 2025年7月31日)