生成AIの進化と普及が半導体業界全体を牽引し、2025年もデータセンターを中心に需要の高止まりが続いている。こうした状況の中、企業間の競争は単なるチップ設計や性能比較を超えて、「どれだけ安定的に製造できるか」という製造インフラの主導権争いへと軸足を移している。
その中で特に注目されるのは、NVIDIAのデータセンター向けGPU「B100シリーズ」などの高性能AIチップに不可欠な先端パッケージング技術と、3nm・2nmクラスのロジック製造を担うファウンドリの前工程外注体制である。
今やこのような供給力こそが差別化の源泉であり、AI開発競争の勝敗は「作る体制をどう確保するか」によって決まろうとしているのだ。本稿ではこのAI開発を左右する“半導体インフラ争奪戦”に焦点を当て、半導体の真の勝者を決める条件などを探る。
パッケージからファウンドリ戦略まで――再定義される「どこで、どう作るか」
2025年4月、NVIDIAの次世代AIチップ「B100」の量産出荷が始まり、市場は再びサプライチェーンの逼迫と向き合うこととなった。また、H100/H200と同様、TSMCの先端パッケージング技術「CoWoS」は供給の要であり、キャパシティの確保が最大の課題となっている。
このため、TSMCは2024年から2025年にかけて、CoWoS製造能力を月産約3万枚から4.5万枚超へ増強。台湾・台中の生産ラインを中心に、既存拠点に加え、新たに獲得した施設も活用して増産体制を整えている。また、SPIL(矽品精密)との委託連携によって一部工程を外部に移管し、ボトルネック解消のための工程分散が進められている。
NVIDIAはこの拡張体制を前提に、TSMCとの協議を重ねるとともに、後工程ではASEやSPILといった後工程(OSAT:Outsourced Semiconductor Assembly and Test)企業との協業を強化。CoWoSの需要急増に対応するための複層的な供給戦略をとっている。
OSATの戦略転換――日系企業の生産体制が世界に再接続
先端パッケージングの需要拡大に伴い、OSATの価値が再定義されている。従来はコスト中心の業界構造だったが、2025年現在は高密度・高放熱・高信頼性を実現する技術的ハードルの高さが評価軸になっている。日系OSAT企業もこうした流れに対応し、供給体制の強化を進めている。以下で各社の動向を紹介する。
新光電気工業:長野や能登に加え、福井工場を2025年春に稼働開始。NVIDIA・AMD向けの多層サブストレート供給を強化。
イビデン:HBM搭載に対応したパッケージ基板の増産体制を確立。米Micron、韓SK hynixとの新規供給関係を構築。
TOWA:FOWLP対応モールディング装置の技術展開を加速し、台湾・韓国・中国のOSATと連携。
これらの取り組みにより、日本企業の装置・材料・基板分野は、「量より質」のOSAT再編の中核プレイヤーとして再び脚光を浴びている。
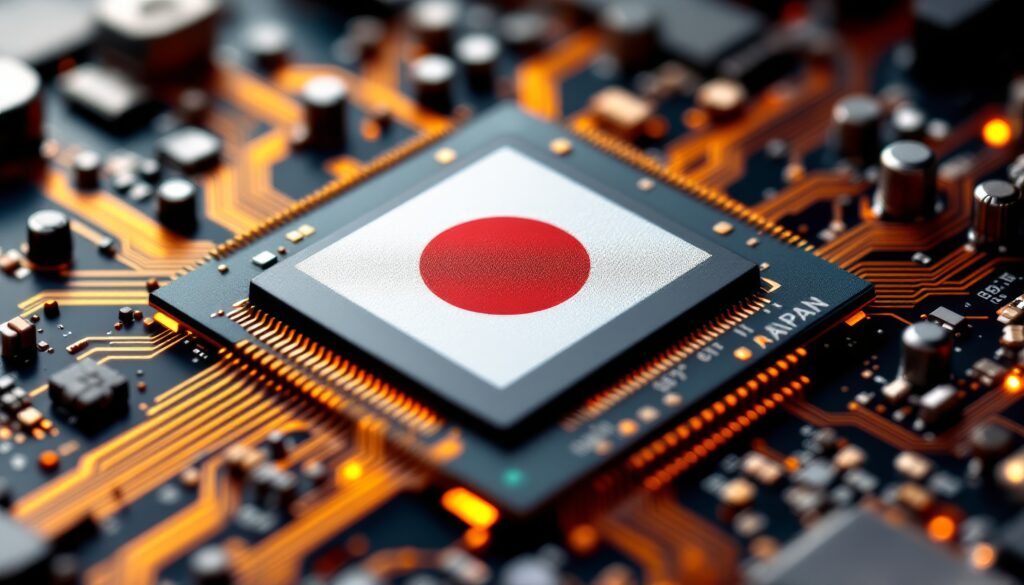
ファウンドリの3強時代――TSMC、Samsung、Intelの攻防戦
前工程を担うファウンドリにおいては、TSMCが3nm・2nmプロセスでの商用実績を背景に依然として優位を維持している。一方で、SamsungはSF3(第2世代3nm)の量産化に成功し、Qualcommなどの大口顧客を取り込む動きを加速。
さらに、Intelも「Intel 18A」(2nm相当)プロセスでテープアウト済みのチップを2025年後半から出荷予定としており、AWSやMediaTekとの顧客契約を背景に外販事業(IFS)の拡大を図っている。
加えて、各社は製造拠点の分散投資を続けており、TSMCの熊本第2工場(JASM第2棟)は2025年内に着工、2027年稼働を予定。地理的リスクを避ける拠点戦略が、製造キャパ確保と同じく開発ロードマップを左右している。
政策と製造地戦略が重なる時代へ――国家の意思が供給網を形作る
半導体製造キャパの拡張は、いまや企業の経済合理性だけでは完結しない。米国ではCHIPS Actによる補助金施策が継続されており、MicronやIntelの国内投資には数千億円規模の政府支援がついている。
日本でもラピダス支援に続き、キオクシアやJASMへの追加補助が経済産業省内で検討中とされており、サプライチェーン再構築が政策と一体の国家戦略として進んでいる。
企業はこれらの動きを見据え、「どこに拠点を構えるか」「どこの支援を得るか」を中長期戦略として明確に位置づける必要がある。
出典:経済産業省 日本国内の半導体支援施策https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0012/handeji4r.pdf

インフラを制する者が開発競争を制す――次に動くのはどこか
2025年、AI半導体を取り巻く競争の本質は、もはや技術仕様では語れない。設計力に勝る製品であっても、製造できなければ市場には届かない。
この構造変化に対応する企業だけが、新たな主導権を握る立場を得る。TSMC、ASE、SPIL、さらには日系OSAT各社との連携のあり方は、開発スピードだけでなく事業継続性と調達安定性を左右する。
製造キャパの確保、後工程の信頼性、地理的リスクの分散。いまやこれらの要素は「技術戦略」ではなく、経営判断の中核テーマとなっている。
AIの未来は、インフラを制した企業が築くと言っても過言ではない。
TMH編集部 坂土直隆