日本の半導体産業、復活の鍵はパワー半導体にあり
日本の半導体産業は、一時期世界を席巻していたが、近年では台湾・韓国・米国などの台頭によりシェアを大きく落としている。しかし、パワー半導体に関しては依然として競争力を持ち、国内外の需要が拡大している。特に、電気自動車(EV)や再生可能エネルギーの普及が進む中で、パワー半導体の市場規模は2030年までに前年比8%以上の成長が見込まれている(出典:Yole Développement, 2023)
本記事では、日本のパワー半導体産業の強みと課題を分析し、再びグローバル市場で存在感を示すことができるのかを考察する。
日本のパワー半導体産業の現状と課題
1.日本の強み:素材・技術・サプライチェーンの優位性
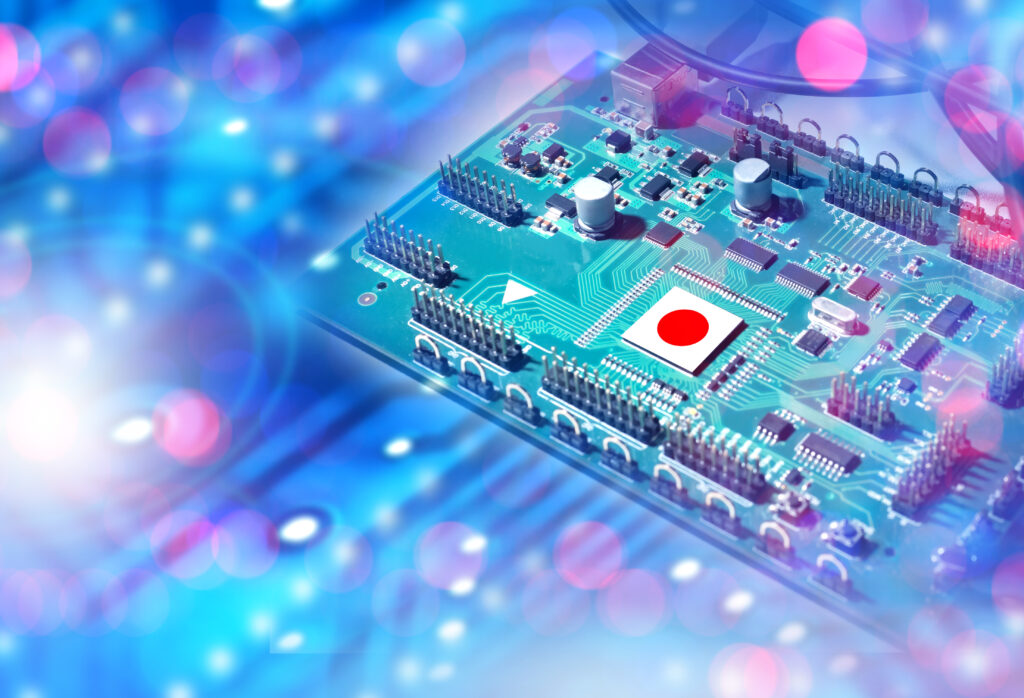
日本はシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)などの次世代パワー半導体材料の分野で強みを持っている。特に、ロームや三菱電機、富士電機、東芝などの企業は、SiCデバイスの開発に注力し、実用化を進めている。市場ではSiCの採用が増え、2027年にはSiCパワー半導体の市場規模が約60億ドルに達すると予測されている(出典:MarketsandMarkets, 2023)
また、日本はウエハー製造技術にも強みを持ち、世界トップシェアを誇る信越化学工業やSUMCOがSiCウエハーの生産を拡大している。さらに、製造装置の分野では東京エレクトロンやアドバンテストといった企業が半導体プロセスの要となる技術を提供しており、国内でのサプライチェーンが確立されている。
2. 最大の課題:設備投資と量産体制の遅れ
一方で、日本の課題は、パワー半導体の量産体制の確立に時間がかかっている点である。海外勢、特に米国のWolfspeedやドイツのInfineonは、大規模な投資を行い、次世代パワー半導体の量産を急速に進めている。例えば、Wolfspeedは2024年までに約30億ドルを投じてSiC工場を拡張しており、日本企業との競争が激化している(出典:Wolfspeed Investor Relations, 2023)
さらに、日本のパワー半導体メーカーは、旧来のシリコンベースの製品からSiC・GaNへの移行に慎重であり、投資決定が遅れるケースも見られる。この遅れが、競争力低下の原因となっている。
3. 巻き返しのチャンス:政策支援とグローバル展開
政府の支援も日本のパワー半導体産業にとって重要な要素である。経済産業省は2023年に「半導体・デジタル産業戦略」を発表し、国内半導体産業の復活を支援する政策を打ち出している(出典:経済産業省, 2023)
また、日本企業は海外企業との戦略的パートナーシップを拡大しつつある。例えば、ロームはSTMicroelectronicsと提携し、SiCパワー半導体の共同開発を進めている。こうした国際的な連携が、日本企業の競争力向上につながる可能性がある。
日本のパワー半導体産業の未来—競争力を高めるために
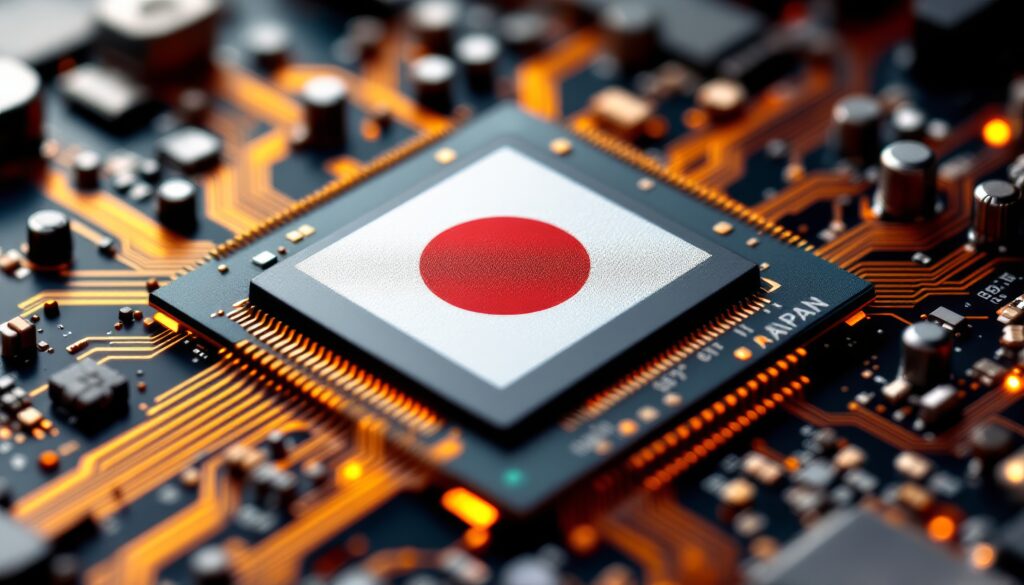
日本のパワー半導体産業は、素材技術やサプライチェーンの強みを活かしつつ、設備投資や量産体制の強化が必要である。また、政府支援や国際的なパートナーシップを活用しながら、競争力を向上させることが求められる。
これからの半導体業界は、EVや再生可能エネルギーの普及を背景にパワー半導体の重要性が増していく。日本企業がこの波に乗り、グローバル市場で再び存在感を示せるかどうかは、今後数年の動きにかかっている。
読者の皆様も、自社の戦略や技術開発の方向性を見直し、パワー半導体の市場動向を注視してほしい。未来の半導体産業を左右するのは、今この瞬間の意思決定かもしれない。