2022年に成立した米国CHIPS and Science Act(総額約527億ドル)は、半導体産業の国内回帰を目的に、大規模な補助金を提供してきた。しかし、現時点で「量産ライン」を実際に稼働させているのは、TSMCのアリゾナ工場(4nm)だけである。
さらにIntelやMicron Technologyは相次いで量産開始を延期しており、このようなことから米国内のサプライチェーン、人材確保、研究体制の課題が明らかになってきた。本稿では、こうした米国の「現場の実態」を整理し、日本企業にとってどのような影響と機会があるのかを再検証する。
米国半導体再建の旗手はTSMCか?―4nmプロセスでの量産を開始
TSMCのアリゾナ第1工場(Fab 21)は、2025年初頭に4nmプロセスでの量産を開始した。N4技術による高歩留まり・高品質の製造体制が構築されており、台湾本社の製造水準と同等に達していると報じられている。
このファブで製造されるのは、AppleのA16チップやAMDの次世代Ryzenプロセッサなど、高性能デバイス向けの製品。経済的波及効果も大きく、6,000人規模の高技能職と、建設段階では2万人以上の雇用を生み出した。TSMCは、米国政府から最大66億ドルの補助金と50億ドルの政府保証融資も受けている。
Intelオハイオ工場は稼働延期―TSMCとの進捗格差が明確
一方で、Intelのオハイオ工場は、当初の2025年稼働予定から大幅に遅れ、2030年以降になると発表された。この延期の背景には、「市場ニーズに応じて投資を行う」プル型投資戦略と、巨額投資による財務リスクを抑える経営判断がある。
こうした動きは、米国が掲げる「先端製造の国内回帰」にとって痛手となっており、実態としてはTSMCとの進捗格差が明確になっている。
MicronのDRAM新工場も稼働は2026年以降―現時点では建設段階
Micron Technologyも、アイダホ州とニューヨーク州で大規模なメモリ工場を建設中。同社はCHIPS Actにより最大61億ドルの補助金を受けており、総投資規模は最大500億ドルと見込まれている。
ただし、2025年6月時点では、いずれも建設段階にとどまっており、本格的な稼働は早くても2026年以降になる見通し。特にEUV露光装置や高純度材料の現地供給、熟練技術者の育成といった点が、ボトルネックになっている。
サプライチェーン再構築と人材・研究体制は遅れ気味
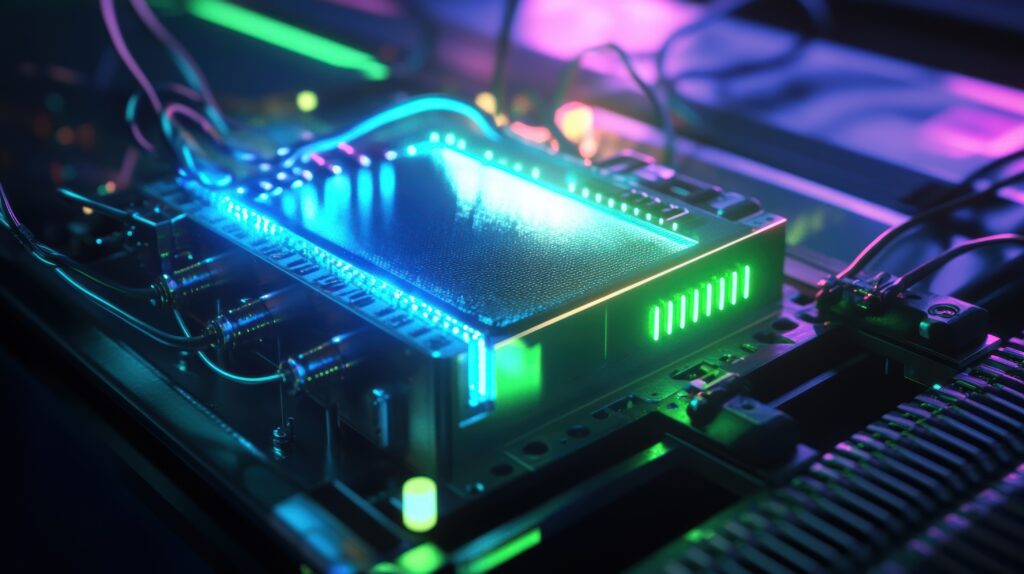
米国内では、先端装置メーカーや材料サプライヤーの多くが国外に位置しており、製造ラインの多くが海外技術に依存している状況。さらに、2nm以降の次世代半導体開発に必要な研究連携や人材育成の制度設計も、整っているとは言えない。
これらの要素が整備されなければ、CHIPS Actによる製造投資も単発の補助金効果にとどまり、長期的な競争力強化は厳しいだろう。
日本企業の「進むべき方向」はTSMCアリゾナとの連携か
TSMCのアリゾナファブでは、すでにAppleが先端SoCを製造する計画を進めており、同社のAdvanced Manufacturing Fundも増額されている。これは、日本企業にとって大きなチャンスではないだろうか。
たとえば、EUV用レジストやスパッタ装置、検査装置、後工程用パッケージング材料など、日本勢が強みを持つ分野においては、TSMCの現地サプライチェーンに参入する現実的な道が開かれていると言える。
新たに米国内に製造拠点を建てるよりも、TSMCと共に稼働中の生産ラインで信頼関係を築く方が、実利に直結する戦略だと思われるからだ。
日本にとって重要なのは実需に即した連携を築けるかどうか
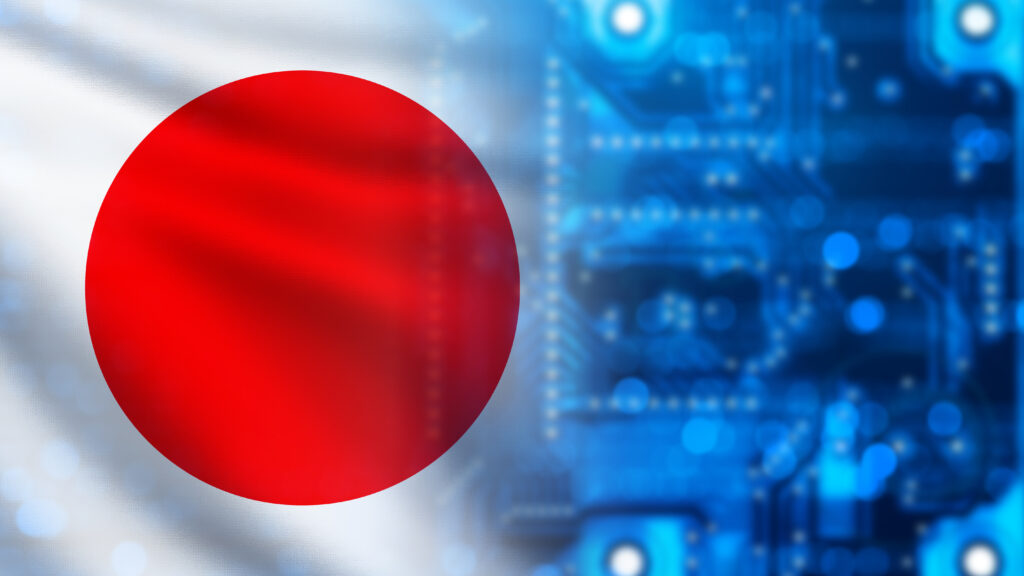
前述のように、TSMCアリゾナ工場が4nmプロセスによる量産を開始したことで、米国CHIPS Actの「実装フェーズ」が現実のものとなりつつある。一方で、IntelやMicron Technologyの計画は大幅に遅れ、米国の半導体製造基盤の再構築にはなお多くの課題が残されている。
こうした中、日本企業にとって重要なのは、補助金や政策の枠組みだけではなく、すでに稼働を始めている製造現場とどう向き合い、実需に即した連携を築けるかという点。
CHIPS Actの真価は、「動いている現場」にこそあるのだ。国境を越えた連携と、日々進化する製造現場への理解こそが、今後の競争力の礎となるはず。今、求められているのは戦略ではなく、現実と向き合う覚悟ではないだろうか。