この1年は、RISC-V(オープンソースの命令セットアーキテクチャ)が「評価」段階から「本格導入準備」段階へ進んだ時期だった。米国系スタートアップの資金調達、メガプラットフォーマーのM&A、人材育成の制度化、エンタープライズLinux対応など、量産に向けた“前提条件”が段階的に整った。
一方、Armアーキテクチャはライセンスプログラムの拡充で参入障壁を下げ、開発着手の容易さを武器に対抗している。本稿は、このような状況の中、MCU・SoC開発において国内企業がどのような戦略と選択肢をとるべきかを考察する。
人材育成:不足する最先端ロジックの設計スキルを体系的に育てる

日本はカナダのTenstorrentと連携し、最大5年間で約200人の設計者を対象とするRISC-VベースAIチップ設計の訓練計画を公表した。国内で不足する最先端ロジックの設計スキルを体系的に育てる施策であり、「アーキテクチャ選好」から「教育・運用の整備」へと議論の重心が動いた最初の事例となった。
人材の“土台づくり”は、その後のツール・標準・参照実装の受け皿になる。加えて、国内企業にとっては採用市場の逼迫を回避しつつ、設計チームをゆるやかに拡張できるという副次効果が大きい。海外人材の短期登用だけでは定着しにくいプロセスノウハウ(設計ルール、テストフロー、セーフティ規格の実装作法)を、国内の共通知識として均質化できる点は、量産立ち上げの速度差に直結する。
RISC-Vの評価向上と実採用状況
2025年2月19日、米国のRISC-Vベース・プロセッサ企業AheadComputingが2,150万ドル(約32億円)の調達を発表した。これで、元Intel系エンジニアが率いる高性能領域への挑戦に資本が付いたことで、RISC-Vが組み込みの枠を超えてデータセンター級計算に接近する地合いが強まった。
同時期、RISC-Vではプロファイル整備や行列演算拡張の進捗が相次ぎ、命令セットの“共通分母”が固まるほど、コンパイラやOS移植の手戻りが減り、導入側の総コスト見積もりが明瞭になった。
さらに3月4日、米国MIPS TechnologiesがRISC-Vを核にIPライセンス+自社チップの二層戦略への転換を発表した。これにより、ロボティクス向けAIチップという参照実装を提示し、ドライバや長期供給に関する不確実性を抑える“動くサンプル”が増えた。そして、エコシステムの信用度が一段上がったと言える。
このようなIP供給にとどまらず自社シリコンで最適化の実例を示す流れは、採用企業の設計判断を速めることになる。評価ボード上で実測の消費電力・スループット・遅延時間の低下を得られることは、当然机上の性能指標よりも説得力がある。
SiFiveとRed HatがRHEL 10へのRISC-V対応を進める

米国のファブレス半導体企業SiFiveと米国のオープンソース企業Red Hatは、「RHEL 10」(Red Hat Enterprise Linuxのバージョン10)のRISC-V対応(Developer Preview)を公表した。評価ボード上でCI/CDや運用テストを現実的に回せる段階に入り、サーバー、ゲートウェイ、産業機器など“Linux前提”の領域で検証が加速した。
対象プラットフォームとして高性能RISC-Vプロセッサを搭載した開発ボード「HiFive Premier P550」が明示され、企業ITで使うLinuxがそのままこと使えることは、調達・保守の社内稟議を通すうえで決定打になりやすい。RISC-Vの“実務適合性”が一段上のフェーズへ移行したと言える。
ここで重要なのは、OSだけでなくツールチェーンと検証資産が縦につながった点だ。すなわち、クロスコンパイルの自動化、コンテナ基盤での再現可能ビルド、ドライバの継続的テストが、既存の社内パイプラインへ最小限の変更で組み込めるようになった。結果として、新規SoCのBring-upから製品QAまでのリードタイム短縮が見込めるようになった。
クラウド/データセンター実装の前進
7月22日にはAIアクセラレータ×RISC-Vの資本・事業連携が発表され、クラウド側の計算資源へRISC-V実装を広げる動きが可視化された。
続く9月30日には、米国MetaPlatformsによる米国Rivos買収計画が報じられ、社内AIチップ群(例:MTIA)との組み合わせで特定ベンダー依存を相対化する構図が見え始めた。RISC-Vが“内部の実運用”に入ると、IP、コンパイラ、ランタイム、OS対応は加速度的に厚みを増す。実装対象がエッジからデータセンターまで連続化し、評価から量産への橋渡しがしやすくなる。
加えて、ソフトウェア資産の水平展開(推論ランタイムの共通最適化、RPC/通信スタックの再利用)が効くため、ハードのマルチベンダー化に伴う運用負荷を相殺できる。企業のCIO/CTO視点では、クラウド〜エッジの一貫したSLO管理が取りやすくなる点が実務的な利点だ。
Armの対抗策
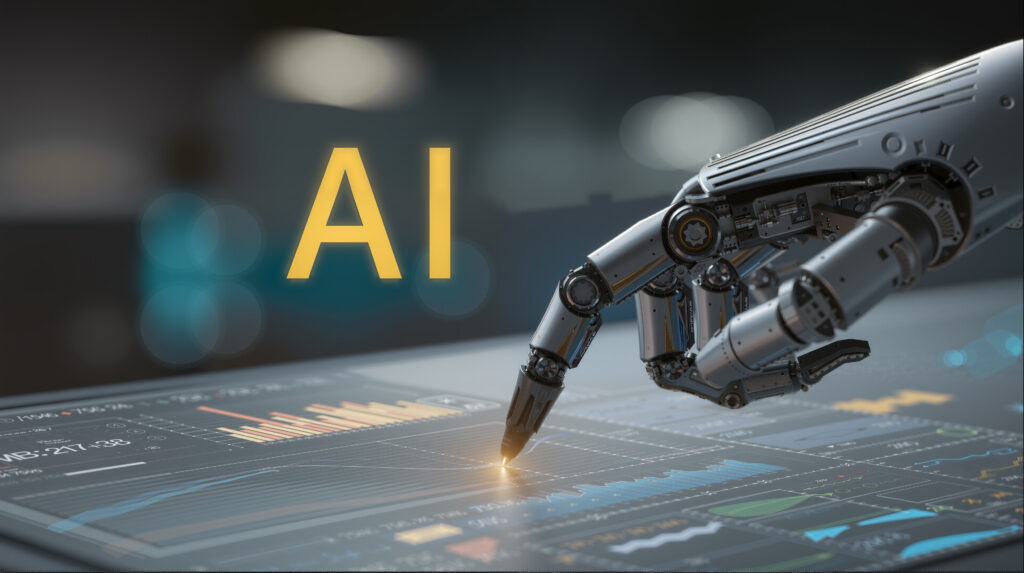
ArmはオンデバイスAIを意識したライセンスプログラムの対象拡大を発表し、設計ツールやIPへのアクセス、トレーニング支援をパッケージ化して初期の時間・費用コストを下げた。RISC-Vが「拡張自由度と差別化」で攻めるのに対し、Armは「着手の速さと支援」で迎撃する。
導入総コストは一言でまとめると、
導入総コスト = 学習・移行(人件費)+ ツール/ボード/OS適合(試作費)+ 量産移行の検証・信頼性(試験費と期間)。
意思決定者が見るべき観点は、①学習・移行コスト、②ボード&OSの即時性、③量産移行の難度(検証・信頼性・ドライバ)、④人材確保の容易さ——の4点に整理できる。ここにソフトの長期保守(セキュリティフィックス、LTSカーネル、コンパイラ更新)も実質的コストとして加わる。
Armの強みは、長年のエコシステムの成熟度とアプリ互換の読みやすさにあり、PoCから量産までの“躓きポイント”の予見性が高い。一方でRISC-Vは、用途特化ブロックの自由度で設計最適点を探りやすく、BOMと電力の抑制が効く。両者のせめぎ合いは“性能”よりも“導入速度と総所有コスト”に移った。
日本MCU・SoCがとるべき戦略とは

では、このような状況に対し、日本のMCU・SoC企業はどのような戦略で対応すれば良いだろうか。以下にまとめる。
提案したいのは、「二正面作戦」ともいうべきものだ。既存のArm系MCU資産(RTOS、ドライバ、安全規格)を中核に保ちつつ、RISC-Vサブシステムで電源管理・セーフティ・軽量AI推論など差別化ブロックを積む。そして、Armの成熟資産とRISC-Vの拡張自由度を併用し、ライセンス条件や供給変動への耐性を確保することがベストではないか。
- ツールチェーンの固定:RISC-V側は行列拡張やプロファイル準拠を前提に、コンパイラ/ランタイムを早期選定。Arm側はFlexible Access等を活かし、試作〜量産フローの時間短縮を図る。
- リファレンス活用:ロボティクスやエッジAIなど“用途特化”の参照実装を検証ラインに取り込み、社内IPの再利用設計を加速。量産認証の観点では、安全規格(ISO 26262/IEC 61508等)の要求分解を早期に固定する。
- サプライと人材:短期はArm、長期はRISC-Vの併走体制が現実的。ボード・OS・ドライバの即応性が高いArm系で製品リリースを確実にしつつ、RISC-V側で社内IPの再利用と新規ブロックの内製化を進め、人材の学習曲線を先に作る。
既存資産・人材・ツールを束ねた二正面作戦で競争力に差を
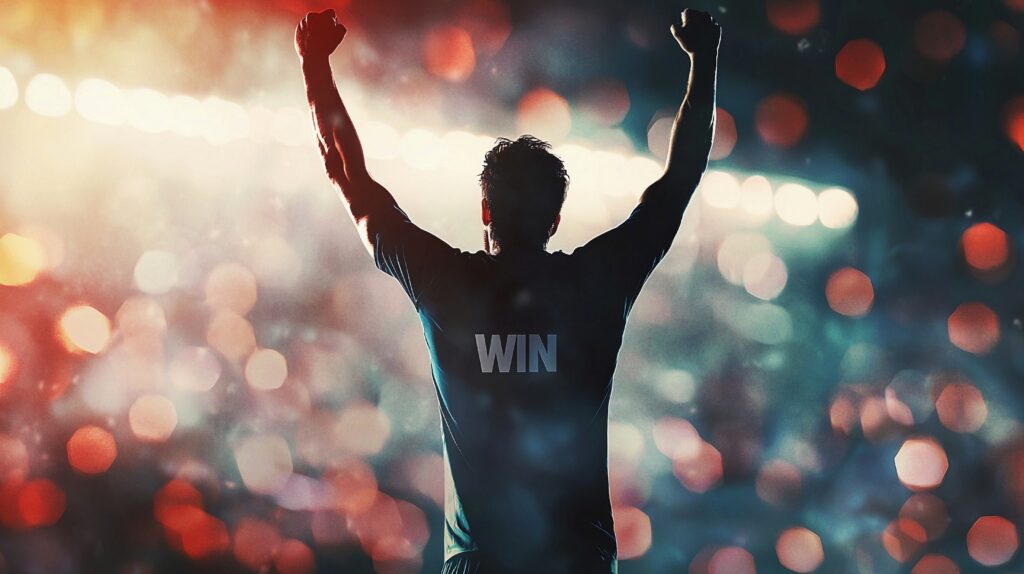
この1年は、人材(Japan×Tenstorrent)、資本と標準、ソフト、実装、そしてArmの対抗が連続した。競争の焦点は、コアのベンチマークではなく、導入までの総コストと検証から量産への移行速度に移っている。
来年度は、RISC-Vサブシステムの量産適用例がエッジから車載・ロボティクスまで増えるだろう。国内の意思決定者は、アーキテクチャ論争ではなく、既存資産・人材・ツールを束ねた二正面作戦を前提に、ロードマップを早期に固定すべきだ。「まず動かし、測って、増やす」。この順序を現場の標準にすることが、競争力の差になるのである。
*この記事は以下のサイトを参考に執筆しました。
参考リンク
- Ex-Intel executives raise $21.5 million for RISC-V chip startup(AheadComputing)
- MIPS shifts strategy toward robots and designing chips
- SiFive Collaborates with Red Hat to Support Red Hat Enterprise Linux for RISC-V
- Red Hat partners with SiFive for a RISC-V developer preview for Red Hat Enterprise Linux 10
- Meta plans to buy chip startup Rivos to boost semiconductor efforts
- Arm expands AI licensing program to boost on-device AI market share
- Unsung FieldsとTenstorrent、資本業務提携を発表
- Japan taps US chip startup Tenstorrent to help train new wave of engineers